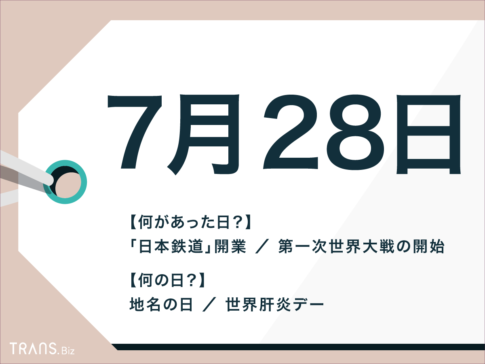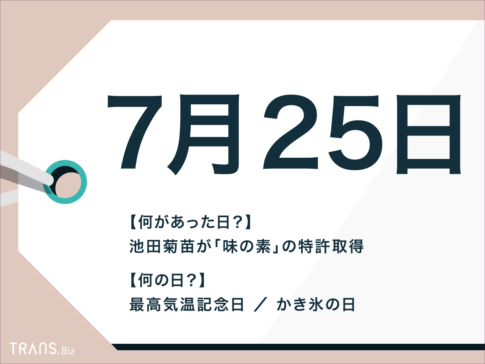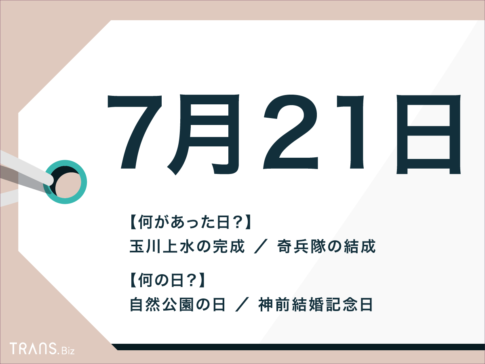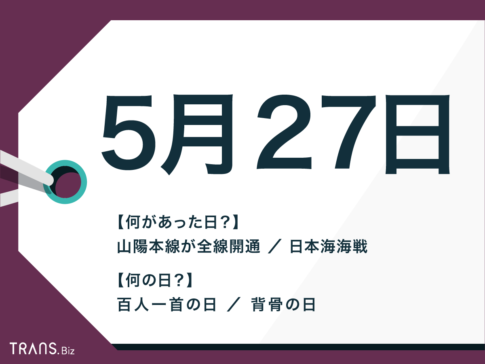「出奔」は一般的には「行方をくらます」という意味で使われる言葉です。また、戦国時代を描いた小説や歴史本などでは、武士や武将に対して使われる特別な言い回しでもあることをご存知でしょうか?
ここでは「出奔」の意味や読み方の他、使い方とその例文、また類語や英語フレーズについてわかりやすく解説します。「逐電」との違いも紹介していますので、ぜひ参考にしてみください。
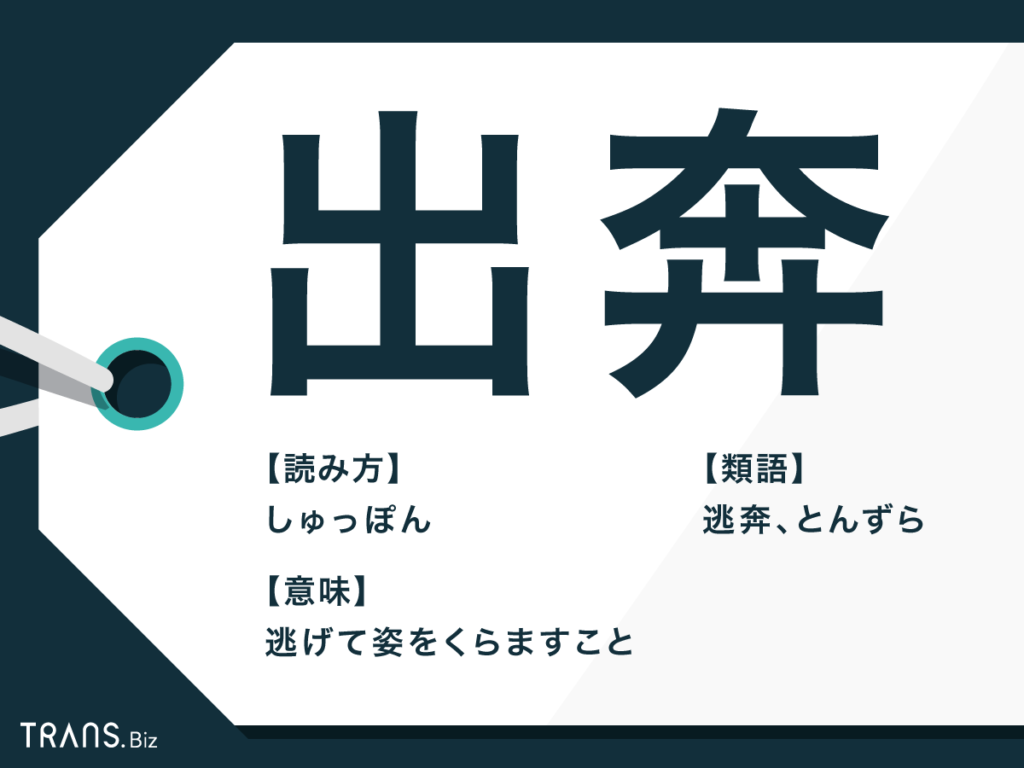
「出奔」の意味と読み方とは?

「出奔」の意味は”逃げて姿をくらますこと”
「出奔」の意味は、“逃げ出して姿をくらますこと”です。つまり、ある場所から飛び出し、行方がわからなくなるさまを「出奔」といいます。
もうひとつの意味は「武士・武将が失踪すること」
「出奔」のもう一つの意味は、“武士や武将など失踪すること”です。江戸時代にはすでに、武士の身分である「徒士(かち)」以上に対して、”逃亡し姿をくらますこと”という意味で使われていました。「出奔」という表現は、戦国時代の小説や歴史本でよく見られるのはこのためです。
「出奔」の読み方は”しゅっぽん”
「出奔」の読み方は“しゅっぽん”です。「出奔」の「出」には”ひっこんでいたものや、隠れていたものが出現する”、また「奔」は”勢い良い・駆け回る”という意味があります。この二つを組み合わせて出来た言葉が「出奔」です。
「出奔」と「逐電」との違いとは?

「逐電」とは”素早く逃げて行方をくらます”
「出奔」と似た表現に”逐電(ちくでん)”があります。「逐電」とは、もともと”稲妻を追う”という意図を持ち、「極めて敏速に行動すること」を指します。転じて「特に素早く逃げ、失跡すること」という意味も持ち併せています。
双方の違いは「スピード」と「素早さ」
「出奔」も「逃げて失跡する」という意味がありますが、「逐電」は”非常にそそくさと、足早に、敏速に逃げて姿を消す”というニュアンスを持ちます。
つまり「出奔」と「逐電」は、基本的には同じ行動を表す言葉となりますが、「スピード」や「敏速さ」において、「逐電」の方が「出奔」よりもニュアンス的に強まる点で異なると言えます。
「出奔」の使い方と例文とは?

「出奔」は一般的な会話では使いにくいことも
「出奔」とは”逃げて行方をくらますこと”という意味がありますが、一般的な会話や文章で使うことは少ないかもしれません。むしろ、表現の硬い小説や、武士や武将の生涯を描いた戦国小説などで使うことが多いといえます。
「出奔」という表現を日常的に使うと、相手に堅苦しい印象を与えることがあります。もちろん、環境や相手にもよりますが、「出奔」を使いにくい時は、意味の通りやすい他の類語に置き換えてみましょう。類語については後の項目でご説明します。
「出奔」を使った例文
「出奔」を使った例文をいくつかご紹介しましょう。
- 両親と口喧嘩をして出奔してしまった。
- 出奔したと聞いたが、行方がわかったそうだ。
- 故郷で暮らすのが苦になり、突然として出奔した。
- 父の出奔で、家族の輪が崩れてしまった。
- 出奔したと言えども、行方がわかるまで捜索するつもりだ。
「出奔」の類語とは?

類語①「逃奔」とは”別の場所へ逃げ去ること”
「逃奔(とうほん)」とは”ある場所から別の場所へ逃げ去ること”を意味します。主に「他の場所へ逃亡すること、逃げること」を表す際に使われます。
「逃奔」と「出奔」はお互い極めて近い意味を持ちますが、「逃奔」は「出奔」より「逃げる」という行動に重点を置く表現となります。つまり、「出奔」が持つ「行方をくらます」というニュアンスが、「逃奔」の場合はやや薄れてきます。
- 国内を逃奔し続けたが、そろそろ金が尽きてきた。
- 彼は地元を離れ、最果ての地へと逃奔してきた。
類語②「とんずら」とは”逃げる意の俗語”
「とんずら」とは”逃げる”という意味の俗語表現となります。たとえば、罪や過ちを犯した人が逃げ去ることや、自分の立場が悪くなった時に、「さっさと逃げ去る」という意味で使われます。
「とんずら」とは「遁(とん)」と「ずらかる」を組み合わせた合成語です。「遁」には”身を隠して逃げる・しりごみする”、また「ずらかる」には”高跳びする”という意味があります。
「とんずら」はビジネスシーンやフォーマルな場で使うのは適切ではありません。日常的な会話や口語でのみ使うようにしましょう。
- 泥棒は盗みをして、とんずらした。
- 飲み会が長引いているので、時間を見てとんずらする予定だ。
「出奔」の英語表現とは?

「出奔」は英語で”run away”や”escape”など
「出奔」を表す英語表現はいくつかありますが、最も使いやすく代表的なのが“run away”や“escape”です。どちらも「逃げ隠れる・姿をくらます」という意味があり、英語圏では使用頻度の高いフレーズとなります。
その他、「姿を消す」というニュアンスを強めたい時は「disappear」、フォーマルで形式ばった表現を用いた時は「abscond」を使っても良いでしょう。
「出奔」を使った英語例文
「出奔」の英語表現を使った例文をご紹介しましょう。
- 私は親と言い争いをして、出奔した。
I run away because I had an argument with my parents. - 出奔したって、また帰ってくるさ。
I believe he would surely come back even though he tries to disappear.
まとめ
「出奔」の読み方は”しゅっぽん”で、「逃げて姿を消し、行方がわからなくなる」という意味を持ちます。また、江戸時代の武士や武将が姿をくらまし、失跡することも「出奔」と呼んでいます。
似た言葉に「逐電」がありますが、「出奔」よりも「敏速に逃げ姿を消す」といったニュアンスが強くなります。上手に使い分けをするようにしてください。
昔の書籍や映画などで「出奔」という表現を見聞きすることがあると思いますが、この機会に正しい意味や使い方をマスターしましょう。