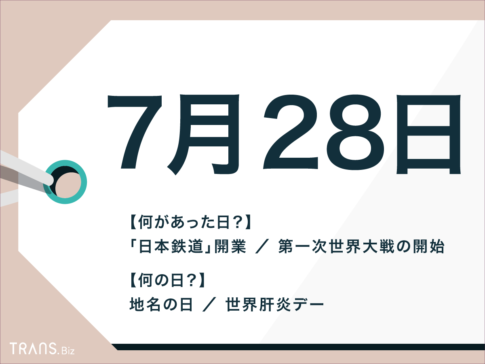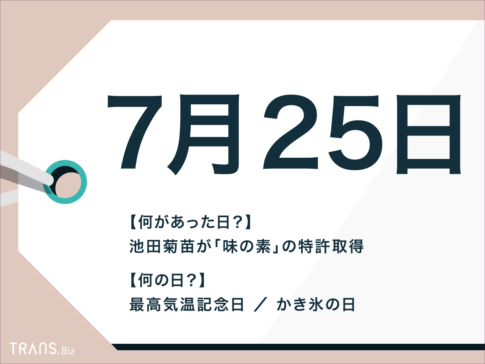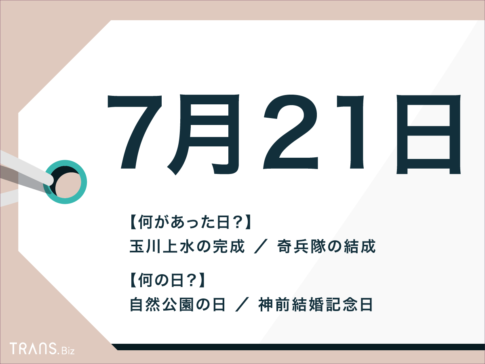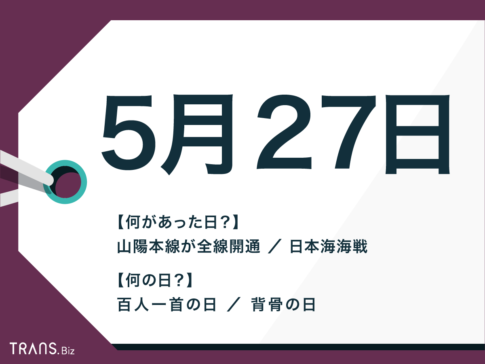「良寛」は、子どもたちと毬をついて遊ぶ優しいお坊さんという、日本の原風景のようなイメージもあれば、清貧の中で優れた俳句や書をたくさん残した孤高の高僧というイメージもある、とらえどころのない僧侶です。
ここでは実際の良寛を俯瞰して、その生涯と書や名言などについて解説します。
「良寛」とは?

まずはじめに良寛について、その生涯と思想を紹介します。
良寛は名家に生まれ幼い頃から『論語』を学んだ
良寛とは、江戸時代後期の禅僧です。幼名を栄蔵といいました。江戸時代に名家に生まれ、幼い頃から聡明で『論語』を学びました。18歳あるいは22歳の時に出家し、曹洞宗の円通寺で修行しました。良寛は恵まれた環境に生まれながらも、その後に自らの意思でその立場を降り、無一物の僧となることを選びました。
良寛は道元の思想に影響を受けた
良寛は「道元」の『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』を精読しており、道元が古代仏教の経典から引いて説いた菩薩行を実行していました。それは「四摂事(ししょうじ)」という菩薩が人々を悟りに導くための、次の四つの方法のことです。
- 布施(ふせ):貪らず分かち合うこと
- 愛語(あいご):優しくいたわる言葉をかけること
- 利行(りぎょう):相手のためになる行いをすること
- 同事(どうじ):人々に協力すること
良寛は特に「愛語」を大切にしていたとされ、人々に交わって愛語の実践を行い、「書」にも書いて残しています。また、良寛の生きた江戸時代は辻説法などが禁じられて布教ができなかったこともあり、子供たちに語りかけることが良寛のできる衆生の救済でもありました。
良寛は生涯を無一物の野僧として過ごした
良寛は道元の徹底した反世俗的な生き方に従い、只管打坐や托鉢を行って修行し、さらには道元も行わなかった、寺を持たず山中に独居する無一物の生涯を送ることを貫きました。その野僧の人生を選んだきっかけについては明らかにされていませんが、父との確執があったともされています。
良寛と子どもの逸話がたくさん残る
良寛にはたくさんの逸話が残されており、中でも子供たちと遊ぶ話が有名です。
良寛は子供たちに仏教説話の「月の兎」の物語を長歌にして、よく語って聞かせました。
【月の兎のあらすじ】
猿と狐と兎の仲の良い3匹が遊んでいると、山の中で倒れている老人に出会った。猿は木の実を拾い集め、狐は川から魚をくわえてきて老人に与えた。しかし兎は何もとってくることができなかったので、猿と狐に火をたいてもらい、炎の中に身を投げて老人に与えた。姿を表した天帝は兎を月の宮殿に連れ帰った。
これは菩薩の自己犠牲による究極の布施と利行を表す物語です。良寛はこのように生きたいと願ったのです。
またよく語られる逸話として、子どもたちとかくれんぼをしていた良寛は藁のかげに隠れたところ、子どもたちは良寛をみつけることができず、家に帰ってしまった。翌日の朝、農夫が藁のところで良寛をみつけ、声を上げると、そんなに大きな声を出すと子供たちにみつかってしまう、と良寛が言った、というものがあります。
「良寛」の書とは?

次に良寛の「書」について説明します。
良寛の書は日本書道の調達点とされる
良寛はたくさんの書を残しており、多くの書跡集が刊行されています。個人の作品集としては他に例がないほどの数が刊行されており、書聖といわれた空海を凌ぐといわれる人気の高さがうかがえます。
良寛の書は、流動性があり自由な書体である草書体を使って、細く繊細で自然美のある書を書くのが特徴とされています。楷書にも優れていましたが、その細く書く独特な技法は良寛独自のもので、日本の書の最高美として高く評価されています。
良寛のかなは「秋萩帖」を手本とした
良寛のかなは、「秋萩帖(あきはぎじょう)」という書の作品を手本としていたことがよく知られています。「秋萩帖」とは平安時代の草仮名の代表的な作品です。良寛が実際に使用して手垢のついた「秋萩帖」や練習作品も現存しています。
「良寛」の名言とは?

最後に、良寛の名言とされる俳句や短歌を紹介します。
良寛の俳句
「うらを見せ おもてを見せて 散るもみぢ」
紅葉が裏や表をみせながら散るように、私も人生の裏と表をさらしながら死んでいくことだ
この歌は、良寛の弟子であった貞心尼(ていしんに)からの歌への返歌として読まれました。晩年、良寛の患った病が重くなったことを聞いて、貞心尼が贈った歌は次のようなものでした。
「生き死にの 境離れて 住む身にも さらぬ別れの あるぞ悲しき」
生死の境界を超えて仏につかえる身にも、避けられない別れがあるのは悲しいことです
貞心尼は良寛が晩年の頃に弟子入りをし、両者には暖かい子弟の交流があり、最期をみとったのも貞心尼でした。
良寛の短歌
良寛はいつも懐に手毬を入れていて、子どもたちと毬をついて遊んだといわれています。その光景を詠んだ短歌を紹介します。
冬ごもり 春さりくれば 飯乞ふと 草の庵を 立ち出でて 里に行けば たまぼこの 道のちまたに 子どもらが 今を春べと 手まりつく ひふみよいむな 汝がつけば 吾はうたひ あがつけば なは歌ひ つきて歌ひて 霞立つ 長き春日を暮らしつるかも
良寛の辞世の句
1831年に良寛は親しい人に見守られながら生涯を終えました。その時、読んだ辞世の句が次の句です。
「形見とて 何残すらむ 春は花 夏ほととぎす 秋はもみぢ葉」
この句は、良寛が尊敬していた道元の次の歌をアレンジした歌です。
「春は花 夏ほととぎす 秋は月 冬雪さえてすずしかりけり」
何の作為もなく、ただそこにある自然の美をありのままに受け入れる素直な気持ちを詠んだ歌で、禅の「不立文字(ふりゅうもんじ)」の精神が根底に流れています。
不立文字とは禅宗の言葉で、教義の伝達は文字や言葉のほか、「体験によって伝えるもの」が神髄であるという意味です。
次のような辞世の句も伝えられています。
「良寛に 辞世あるかと 人問はば 南無阿弥陀仏と 言ふと答へよ」
まとめ
良寛の禅宗への信仰心を知らないまま、残された逸話だけで人物像を構成すると、ただ子どもと無心に遊ぶ、ありがたいお坊さん、という捉え方になってしまうのかもしれません。しかし内には道元への強い帰依があり、「愛語」を生きることによって自らの存在意義を見出し、歌や詩をつくる動機になっていたといわれています。
良寛と弟子の貞心尼との交流を瀬戸内寂聴が小説にしています。良寛が本当は何を思って生きていたのかはわかりませんが、卓越した感性の語り手によって、この時代に生きた人の心のうちを感じとることができるかもしれません。
■参考記事「道元」の思想とは?著書「正法眼蔵」や名言と言葉も紹介