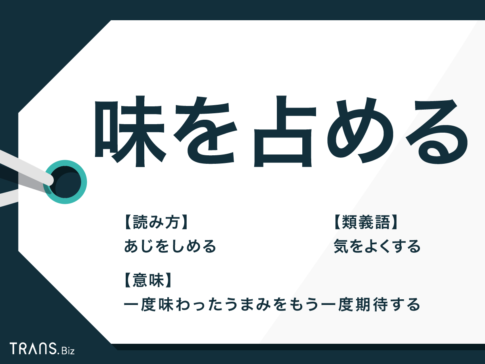ビジネスでは「折衝する」「折衝が行われた」という言い方をすることがあります。この「折衝」とはどういった意味なのでしょう。「折衝」の意味やその内容、また、交渉・渉外など、ビジネスシーンでよく使われる類語との違いについて解説します。

「折衝」とは?

「折衝」は「せっしょう」と読みます。まずはその言葉の意味から紹介します。
意味は「納得できるよう折り合いをつけること」
「折衝」の意味は、「納得できるように話し合い、折り合いをつけること」です。問題解決のための駆け引きや話し合いを「折衝」といい、お互いの納得のために「妥協する」というニュアンスを含む言葉です。
由来は中国、語源は「矛先を折る」こと
「折衝」は、元々は中国から来た言葉です。「衝」には「衝く(突く)」という意味があり、孔子が使った「相手が衝いた矛先を折る」という言葉が由来とされています。
また、宴会の席で偵察に訪れていた敵国の戦意をくじいたという「晏子春秋(あんししゅんじゅう)」のエピソードから、「宴の席に由来する言葉」として紹介されることもあるようです。
利害が異なる相手で使うのがポイント
「折衝」は、単なる話し合いではなく、お互いが妥協し、納得できるようにするというニュアンスがあります。そのため、利害が異なる間柄で使用されるのが特徴です。互いの利益のために、落としどころをどこにするか話し合う、というのが「折衝」です。
個人間での話し合いには使わない
「折衝」という単語は、個人が参加する話し合いでは使用しません。個人対個人はもちろん、個人と会社にも使用しないので注意しましょう。「折衝」は国と国、会社と組合などにおける公的な話し合いに対して使用します。規模も大きいのが特徴で、政治や経済、資金(お金)の話題に使われるのが一般的です。
「折衝」の使い方と例文

「折衝」の言葉の意味が分かったところで、実際のビジネスでの使い方を紹介します。
ビジネスでは有利になるよう折り合いをつけること
「折衝」は利害の異なる間で使うことは先述しましたが、ビジネスでも同様で、納得できるよう話し合うことを意味します。さらに、ビジネスでは、自分(自社)に有利になるように折り合いをつける、というニュアンスが加わるのが特徴です。
「折衝する」「折衝が行われる」が一般的
「折衝」は、「折衝する」「折衝が行われる」という表現が一般的です。たとえば、
- 先方と折衝するのが私の役割だ
- この件について折衝が行われるのは当然のことだ
といった使い方がされています。
「折衝業務」とは顧客との合意点を見つける調整役
ビジネスでは、「折衝業務」「顧客折衝」という言い方もあります。いずれも、顧客と見積もりや納期、発注内容などについてやり取りをし、その合意点を調整するのが仕事です。
単に相手の要望を反映させるだけでなく、自社にも有益となるような駆け引きが必要になるため、一筋縄ではいかないこともあります。
「折衝力」の鍵はコミュニケーションと調整
折衝する能力やスキルは「折衝力」と呼ばれます。「折衝」にまず必要なのは「コミュニケーション力」です。相手の意見を聞き出すことはもちろん、こちらの要望を的確に伝えるスキルが必要です。
お互いの意見が出そろったら、落としどころどこにするのか、どう納得してもらうのかといった「調整力」が求められます。ただ要求を鵜呑みにしたり、要望を押しつけたりするのではなく、納得のいく妥協点を探しだし調整する力が必要です。
「折衝」の類語、違いとは?

「折衝」の類語には、協議・駆け引き・取引といった言葉があります。中でも、「折衝」と同じくらいよく耳にするのが「交渉」です。
「交渉」は利害関係を問わない
「交渉」と「折衝」は、語感は似ていますが、ニュアンスが異なります。先述したように、「折衝」は利害が異なる間で使います。一方の「交渉」にも、互いが納得するまで話し合う、という意味がありますが、利害が一致している場合でも使用できる言葉です。
「交渉」がスムーズにいけばお互い妥協することなく終了しますが、「折衝」は利害が異なるため妥協が伴うのが特徴です。また、「交渉」は規模や内容を問わずに使用できますが、「折衝」は先述したように個人間では使用しません。そういった意味では、「交渉」のほうが広い意味で使用できます。
「渉外」は外部と交渉すること
「折衝」「交渉」と似た言葉に、「渉外」があります。「渉外」とは、外部と交渉するという意味の言葉で、「国際渉外担当」というと外国相手に折衝する担当者という意味です。
また、法律でも「渉外」という言葉を使うことがあり、「渉外契約」というと二ヶ国以上にわたる契約などを指し、「渉外弁護士(外国がかかわる案件を専門とする弁護士)」という言葉もあります。
一部業界では営業部=渉外部
「渉外」とは主に外国との折衝に関して使われていますが、銀行や百貨店など一部の業界では「渉外部」という部署名が使用されています。銀行や百貨店においては、特定の顧客を対象とした営業活動を「渉外」と呼ぶためです。
一般的な企業の営業部が幅広い顧客を扱うのに対し、「渉外部」の顧客は対象が限られているのが特徴です。独特な使い方ですので覚えておきましょう。
「折衝」の英語とは?

ビジネスシーンでは、英語をそのままカタカナ語として使用する例も増えていますが、「折衝」を英語でいう場合にはどうなるのでしょう。
英語では「negotiation」
「折衝」を英語にすると、「negotiation」になります。「this matter is now under negotiations」で、この件は現在折衝中です、という意味です。「We negotiated with a new company」で、新しい取引先と折衝した、という意味になります。
なお、「negotiation」には「折衝」という意味のほか、「交渉」という意味もあります。日本語ではニュアンスの異なる言葉でしたが、英語では同じ単語を使うというのも覚えておきたいポイントです。
まとめ
「折衝」は利害が一致しない間柄で、納得がいくよう話し合うことを指します。妥協を含むことになるため、駆け引きが必要となります。また、ビジネスではとりわけ、自分に有利になるようにするというニュアンスも含み、折衝業務を任された場合にはその手腕が大きく問われることになるでしょう。