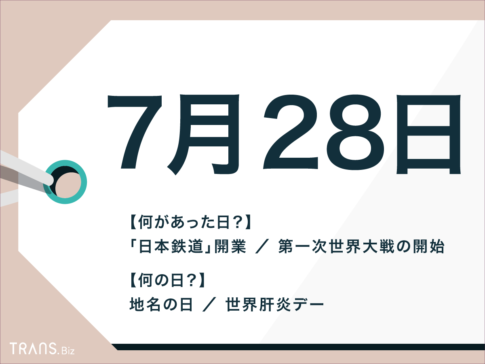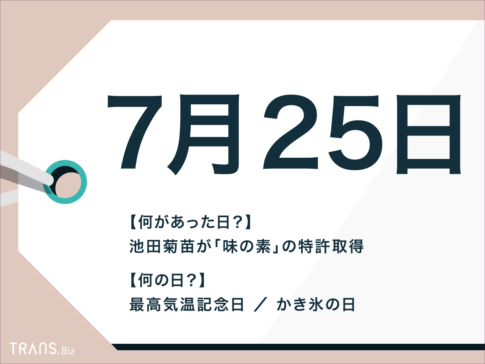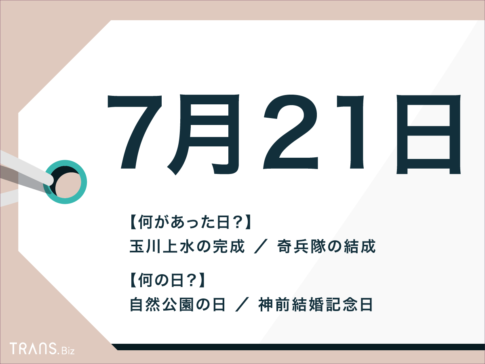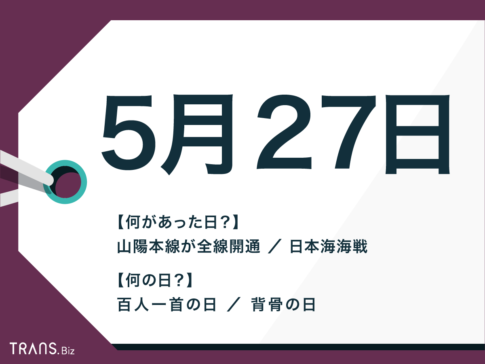「プラトン」は誰もがその名前を知っている古代ギリシャの哲学者です。「ソクラテスの弟子」や「イデア」などのキーワードはよく耳にしますが、プラトンの全体像はあまり知られていないかもしれません。ここでは、プラトンとその思想について、概要を解説します。
「プラトン」とは?

まずはじめに、プラトン(紀元前427年~347年)とはどのような人だったのかご紹介しましょう。
プラトンは「ソクラテス」の弟子として哲学を始めた
プラトンとは、古代ギリシャの哲学者です。またソクラテスの弟子でもありました。プラトンが28歳のとき、神を敬わず、若者を堕落させたとの罪でソクラテスに死刑判決が下され、ソクラテスは毒を飲んで刑死します。それに衝撃を受けたプラトンは、ソクラテスの語った内容を対話篇という形で書き記すことを始め、ソクラテスの哲学とは何だったのかを考え続けます。
「レスリング」の先生がプラトンと命名した
プラトンの本名はアリストクレスで、「プラトン」はニックネームでした。命名したのはプラトンにレスリングを教えていた体育の先生で、プラトンの体格がよかったため、「肩幅が広い」という意味の「プラトン」と呼びました。プラトンはリングネームだったということになります。
プラトンは「ピタゴラス」に影響を受けた
ソクラテスが刑死した後、プラトンも危険な立場となったためアテナイから亡命し、12年間遍歴の生活を続けることになります。その放浪の中で、プラトンはピタゴラス学派の人々と出会います。
「ピタゴラス」とは、三平方の定理で有名な数学者です。「数によって森羅万象を説明できる」というピタゴラスの思想は、プラトンに大きな影響を与えました。
ピタゴラス教徒にとって全宇宙は数学の図式に従って動いているものでした。そして、ピタゴラス学派が「数」としていたものは、プラトンの哲学では「純粋なイデア」として展開されます。「イデア」についてはのちほど説明します。
プラトンは世界最初の大学「アカデメイア」を創立した
アテナイに戻ったプラトンは紀元前386年にアカデメイアの森を購入し、アカデメイア(アカデミー)学園を開きました。これが世界最初の大学とされ、アカデミーの語源となりました。
プラトンのアカデメイアは「哲学」を学ぶ場でしたが、「哲学」という学問を成立させたのがプラトンです。プラトン以前には「哲学者」」という職業も存在していませんでした。
アカデメイアで実践されたのは「問答法」と呼ばれる、議論によって真偽を検討する対話です。問答法はソクラテスの対話の精神を受け継いでプラトンが整備した手法です。
「アリストテレス」はプラトンの学園で学んだ
アリストテレスはプラトンの学園、アカデメイアに入門して学びました。アカデメイアは出身地や身分を問わない自由な校風で、外国からの学生も多く、アリストテレスもマケドニアの出身でした。アリストテレスはプラトンの「問答法」は哲学の訓練にすぎず、それは本当の哲学である形而上学の準備であると考え、やがて独自の哲学を打ち立てます。
両者の違いは、プラトンのイデアは想定された世界でしたが、アリストテレスは現実に存在するものの、それぞれの内にイデアが存在するとしたことです。
「プラトン」の「イデア論」とは?

プラトン哲学の中核となる思想であるイデア論について、次に説明します。
プラトン哲学の中心「イデア」は「永遠の真理」
プラトン哲学の中心は「イデア論」であり、プラトンは生涯イデア論を発展させました。イデアとは、「かたち」「形相」ともいわれ、人が知覚する事象は単なる仮の姿であり、真実の世界は非物質のイデアの世界であるとしました。
つまり、人間が感覚で捉える世界は常に変化し続けるが、精神が捉える普遍的な世界は、変化しない永遠の真理であるということです。
そして、イデアの世界には序列があり、低次のものからより純粋な抽象的イデアへと上昇するといい、その頂点を「善のイデア」としました。そのことでプラトンは精神を理性的なものへ上昇させなければならないと啓蒙したのです。
「イデア」は「すでに知っていること」
さらに、プラトンは「想起説」という魂の輪廻説を展開しました。それは魂はすでに別のところで多くのことを見て知っているはずだということから、人間が学んで知ることは、すでに知っていることを思い出すことだ、という説です。そしてその「すでに知っていること」を「イデア」と呼びました。
「想起説」は、イデアは現実の世界に存在するものではなく、この世ではない別の世界に本当に正しい世界が存在することを裏付けたため、「イデア論」は、現実の汚れた地上世界と清らかな神の国というキリスト教の概念と重なり合い、キリスト教を根底とした伝統的な西欧哲学の中心にイデア論が据えられることになりました。
プラトンの代表作『国家』とは?

プラトンの著作で代表作とされるのが『国家』です。次に『国家』について説明します。
『国家』の副題は「正義について」
『国家』の副題は「正義について」です。プラトンは『国家』の中で「正義とは何か?」について、ソクラテスに語らせています。ソクラテスは理想的な社会として、正しい社会、正義の社会であるユートピアについて語り、正義の社会に生きれば、誰もが幸福になれると語ります。
さらにプラトンは、イデアを知る哲学者が国家を統治するのにふさわしいとして、哲学者を頂点とする国家を理想として示しました。
「洞窟の比喩」で常識からの転換を示す
『国家』の中に書かれる「洞窟の中の囚人たち」の比喩は、哲学史上もっとも有名な比喩とされています。プラトンは、学ぼうとしない人々を「洞窟の奥に繋がれて、影絵しか見ることができない囚人」とソクラテスに例えさせます。
囚人たちは、洞窟の後方の壁しか見ることができないように縛られています。囚人の背後には火が灯され、その後ろにある通路に彫像や人形が運ばれてゆきます。これらの物体の影は、囚人たちの見ている壁に投影され、囚人たちはその影を実在だと認識します。
縄を解かれた囚人は、振り向いて人形そのものや火を目にし、そのとき洞窟からの上昇が始まります。解放された囚人は、光の世界に連れ出され、見慣れない世界に圧倒されますが、徐々に太陽そのものを見分けることができるようになります。これが善のイデアそのものの知であるとするのです。
この比喩は「常識」からの転換を示し、また、真実を認識するには段階を追わなければならず、「現実の世界は影絵である」ということを理解するには長い訓練が必要であることを示しています。
プラトンは「魂」を3つの層で考え「国家」と対比させた
プラトンは人間の魂には3つの層があるとしました。これは魂の三分説(さんぶんせつ)とも呼ばれ、『国家』の中で示しました。人間の魂の性質を、哲学者、活動的な人間、肉体労働に携わる人間の層に分け、魂の3つの部分が自らの役割を果たさなければ正しい人間にはなれないとし、同時に国家の3つの層が自らの役割を果たさなければ、国家に正義は実現しないとしました。
正しい人間であることと、正しい国家であることに相違はないと説いたのです。
「プラトン」の著書を紹介

最後に、プラトンの『国家』の他の代表的な著書を紹介します。プラトンの著作は主に対話で構成される対話篇ですが、その特徴としてソクラテスが対話を導き、その著者であるプラトンはその対話に加わらないということがあります。
プラトンが投げかける「問い」について、読者はソクラテスの対話を通じて考えることになります。
ソクラテスの弁明
『ソクラテスの弁明』では、「国家の信ずる神々を信ぜず、さらに青少年を堕落させた」と告発され、裁判で弁明するソクラテスの姿が描かれます。この告発に対しソクラテスは反論しますが、最終的に死刑が宣告されます。
クリトン
『クリトン』は『ソクラテスの弁明』の続編です。死刑を待つ牢獄の中で、旧友クリトンはソクラテスに脱獄を勧めますが、ソクラテスは「脱獄という不正を犯さないために」それを拒みます。本編は正義とは何かについて述べられています。
メノン
『メノン』の副題は「徳について」です。メノンがソクラテスに「徳は教えることができるのか」と問うところから対話篇が始まります。ソクラテスは徳とは教えるものではなく、神によって与えられている思惑であり、それを思い出そうと学び続けることが哲学であると結論づけます。
饗宴
『饗宴』の原題は「シンポシオン」で、「一緒に飲む」という意味です。ソクラテスとそこに集まった人々が「愛(エロス)」について語り合う内容で、愛はフィロソフィア(知恵の愛)にまで高まるとソクラテスが説きます。ここでもイデア論と、エロスの力がイデアの認識をもたらしてくれることが書かれています。
パイドン
『パイドン』は、ソクラテスの刑死の日の早朝、ソクラテスに別れを告げるため牢獄に集まった弟子たちとソクラテスが、日暮れまで魂の不死について対話した内容を書いた対話篇です。そこにいたパイドンが、その様子を伝えるという形式で書かれています。
死は魂の消滅ではなく、霊魂の肉体からの解放である、と語られた本編の副題は「魂の不死について」です。
まとめ
プラトンは、師であるソクラテスの刑死に衝撃を受け、ソクラテスの対話篇を書くことによって、ソクラテスの哲学を考え続けました。プラトンは、ソクラテスの「善をなすことが幸福である」という哲学を受け継ぎ、「善のイデア」論を示しました。善のイデアに到達すると、神秘的な理解ができるとされます。
これはプラトンよりおよそ100年ほど前に生きた釈迦(ブッダ)が説いた悟りの境地と同じであるとも考えられます。この古代の時代には、神々と対話ができる人がいたとされており、ソクラテスもそのような人であったのかもしれません。